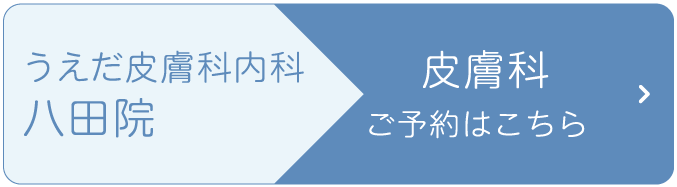多汗症とは
About
多汗症とは、手のひら、わき、足の裏などの限られた部位、または全身に多量の汗が出る疾患です。汗は体温調節を行っています。体温が上がると汗が出て、汗の気化熱で体温を下げます。必要以上に汗が出て皮膚の表面が汗で濡れてしまう状態を多汗症といいます。
多くの場合、小児期に発症し、成人になっても症状が続きます。一般的な小児疾患と違い、15歳ごろになっても症状がおさまることは少ないです。
常に汗が出ているわけではなく、多汗と無汗の状態が交互にみられます。精神的緊張や、気温や運動による体温の上昇をきっかけに多汗になります。
体の左右で同時に発汗します。発汗しやすいのは、手のひら・顔・わき・足の裏・頭部の5か所で、通常、複数の部位で多汗になります。
多汗症の種類
Type
汗には、温度が高い時に出る温熱性発汗、精神的に緊張した時に出る精神性発汗、辛いものを食べた時に出る味覚性発汗があります。
また、原因になる病気があって多汗が生じる続発性多汗症と、とくに病気がなく健康な人に発生する原発性多汗症とがあります。さらに、多汗部位が全身に広がっている全身性多汗症と、体の一部で発汗が増えている限局性多汗症とがあります。
限局性多汗症は、多くはわきの下、手のひら、足の裏に発生します。これらの部位は精神性発汗部位であり、精神的な緊張により発汗が増えます。手のひらの多汗の人は手で触れるものが汗で濡れるために、書類などが濡れて困るなど日常的に困る場面が多くみられます。また、他人に手を触れることを避け、劣等感をもっていることもあります。 全身性多汗症では、甲状腺機能亢進症や褐色細胞腫などの内分泌・代謝性疾患、その他 悪性腫瘍、感染症、中枢神経疾患などが原因になっていることがあります。
多汗症のレベル
多汗症にはレベルがあり、以下のように分類されています。
- レベル1(軽度) 触ると皮膚がしっとり湿っている、または皮膚が濡れてツヤツヤして見える
- レベル2(中度) 皮膚の上で汗が水滴を作っているが、滴り落ちるほどではない
- レベル3(重度) 汗をかく状況ではなくても、水滴となった汗が皮膚から滴り落ちる
レベル1は、自分では汗が多いと自覚していても他人には気づかれないことが多く、生活するうえでも大きな問題にはなりません。しかし、レベル2やレベル3になると、日常生活に支障をきたすだけではなく、人とのコミュニケーションに影響がでることもあります。
多汗症のレベル判定のために用いられる検査の代表的なものにHDSS(Hyperhidrosis disease severity scale)があり、これは、重症度の判定に多く利用されています。
- スコア1 発汗は全く気にならず、日常生活に全く支障がない
- スコア2 発汗は我慢できるものの、日常生活にときどき支障がある。
- スコア3 発汗はほとんど我慢できず、日常生活に頻繁に支障がある。
- スコア4 発汗に我慢ができず、日常生活に常に支障がある。
上記のように、患者さんの自覚症状と日常生活への支障の程度からレベルを判定し、スコアが3と4の場合、重症とされます。
多量の汗に困っていても ただの汗っかきと思って見える方は少なくありません。
手のひらや足の裏がいつも湿っている方
緊張すると多量の汗をかく方
手汗で書類やテスト用紙がにじんでしまって困っている方
腋汗で服に汗じみがついてしまう方
是非ご相談ください。
多汗症の治療
Treatment
多汗症の治療法には外用薬治療、水道水イオントフォレーシス、ボツリヌス毒素皮内注射治療・交感神経遮断治療などがあります。(クリニックでは交感神経遮断治療は行っていません)
外用薬での治療
抗コリン外用薬
外用抗コリン薬は、もうひとつの第一選択として使用されている外用薬です。交感神経からの汗を出す指令を汗腺が受け取れないようにすることで、発汗量を減らします。2020年には、外用抗コリン薬のエクロック®ゲル(5%ソフピロニウム臭化物)、ラピフォートワイプ2.5%(グリコピロニウムトシル酸塩水和物)アポハイドローション(オキシブチニン塩酸塩)が保険適用となりました。発汗もほぼコントロールできるようになり、塗った部分にだけ作用するため、副作用が少ないことも利点です。
塩化アルミニウム製剤
治療の第一選択として推奨されている塗り薬です。皮膚の表面に塗り、汗の出口にふたをつくって汗を閉じ込めます。ただし、かぶれの副作用がみられ、発汗量が多い場合は効果が限定的となることがあります。また、健康保険適用外のため、自費での処方となります。
内服薬での治療
抗コリン薬
プロバンサインは、日本で唯一、多汗症に対する保険適用を有する抗コリン薬です。
エクリン汗腺の交感神経から発汗の指令を受け取る部分をブロックすることで、発汗を抑えることが期待できます。
以下の方は服用できません。
- 閉塞隅角緑内障の患者
抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがあります。 - 前立腺肥大による排尿障害のある患者
抗コリン作用により、交感神経が優位になり、膀胱括約筋収縮・排尿筋弛緩のため、排尿障害が悪化するおそれがあります。 - 重篤な心疾患のある患者
心拍数が著明に増加するおそれがあります。 - 麻痺性イレウスのある患者
腸管の運動機能を抑制し、閉塞状態を悪化させるおそれがあります - 小児に適応はありません
- 抗コリン作用による眼の調節障害、口渇、便秘、排尿障害等があらわれやすいので、運転など危険な行為を伴う作業はしないようにしなければいけません。
漢方治療
発汗をおさえる漢方を、個人の体質に応じて内服していただきます。
水道水イオントフォレーシス
手のひら、足底の多汗症の治療に適した方法です。多汗部位を水道水に浸し、直流電流を流します。通電することにより生じる水素イオンが汗の孔を小さくして発汗を抑制すると言われています。

ボトックス注射
ボツリヌス毒素を皮内に注射すると、エクリン汗腺の活動を抑制し、汗の分泌を抑えることができます。ボトックスは、ボツリヌス菌から抽出されたたんぱく質の一種で、アセチルコリン分泌を阻害して、汗の分泌を抑える働きがあります。以前から、眼瞼けいれんの治療のために用いられてきた薬でありますから、安全性の高い薬剤です。汗の分泌を抑えることで、においも減らすことができます。腋窩に細い針で細かく皮内に注射していきます。