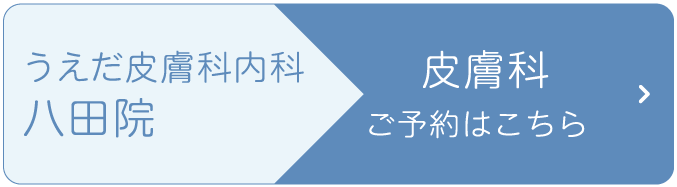虫刺されとは、吸血性の蚊、ブヨ、ダニ、ノミや、身体に毒を持ったハチ、毛虫、ムカデ、クモなどに刺されて起きる皮膚炎のことで、医学的には「虫刺症(ちゅうししょう)」といいます。虫に刺されることで、虫の毒液や、虫の唾液成分などの異物が皮膚の中に侵入し、皮膚に炎症が起きます。
皮膚炎の症状
About
虫によって生じる皮膚炎の多くは、異物に対する生体の防御反応であり、その発症機序から刺激性とアレルギー性に分けることができます。
虫刺されによるアレルギーには、刺された直後から症状が出る「即時型反応」と、翌日などしばらく後に症状が出る「遅延型反応」があります。即時型反応によるかゆみや発赤、腫れは数時間程度で治まります。遅延型反応によるかゆみや発赤、ブツブツは数日から1週間程度で軽快します。
注入された毒液の種類や量、アレルギー反応の有無、年齢や体質によって、症状の程度には個人差があります。
虫の種類
Type
蚊、ブヨ、ダニ、ハチなどの虫が人間の皮膚を刺し、咬み、または人間の血を吸うことによって痛み、かゆみ、赤み、腫れなどが生じることを「虫さされ」といいます。また虫だけでなくクラゲやヒトデに刺されることでも腫れやかゆみが起こります。
- 刺す虫:ハチ
- 咬む虫:ムカデ、クモ
- 吸血する虫:蚊、ブヨ、アブ、ノミ、マダニ
虫さされの原因とメカニズム
虫が皮膚を刺したり咬んだりしたときには、虫が持っている毒成分・唾液成分が抗原(アレルゲン)となってからだの中の抗体と反応し、ヒスタミンなどのかゆみの原因物質が分泌されてかゆみや炎症などの皮膚炎を引き起こします。
つまり多くの虫さされで見られる「かゆみ」は、虫の毒成分などに対するアレルギー反応の一つなのです。
また、毒成分が注入されるときの物理的な刺激や、皮膚に注入された物質の化学的刺激によって、炎症が生じます。これが虫さされの「痛み」の原因です。
このような症状は年齢や刺された頻度、体質による個人差が大きいものですが、一般的にアレルギー体質の人は症状が強く出るといわれています。
代表的な虫の特徴
蚊
人家周辺、山野のみならず、家の中、公園など、どこにでも生息します。刺されてすぐにかゆくなる即時型反応とあとで症状が出る遅延型反応があり、刺された頻度や年齢などにより、あらわれ方に差があります。
ブヨ(ブユ、ブトともいう)
体長2~4mm程度の小型のハエのような黒い虫で、高原や山間部の渓流沿いにいます。朝夕に活動することが多く、特に露出したすね付近を刺される人が多いようです。刺されたあと、かゆみや痛みが徐々に広がり、赤く腫れて赤いしこりが長く続いたり、内出血のような皮疹になることがあります。
イエダニ
主にネズミに寄生するイエダニによる被害が多いです。体長0.7mm程度で布団に潜り込んでわき腹や下腹部、太腿の内側などから吸血し、かゆみの強い赤い丘疹ができます。
マダニ
マダニ類は、比較的大型(吸血前で3mmから4mm)のダニで硬い外皮に覆われており、吸血すると10mmから15mmになります。(家庭内に生息するダニの多くは、0.5mm以下です。)
日本でも全国的に分布しており、主に森林や草地等の屋外に生息していて、市街地でも見られることがあります。マダニに咬まれないようにすることが重要です。
予防策として、草むらや藪など、マダニが生息する場所に入る場合には、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用して肌の露出部分を少なくしましょう。
屋外活動後はマダニに刺されていないかを確認しましょう。マダニ類の多くは、人や動物に取り付くと、皮膚にしっかりと口器を突き刺し、長時間(数日から、長いもので10日間)吸血します。吸血中のマダニを見つけた場合は、自分で取ろうとせず、できるだけ医療機関(皮膚科)で処置しましょう。(無理に引き抜こうとすると、マダニの一部が皮膚内に残ってしまい化膿することがあります。)
マダニに咬まれた後に、発熱等の症状があった場合は、医療機関を受診しましょう。
重症熱性血小板減少症候群(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome:SFTS)は、ウイルスを持っているマダニに咬まれてから6日~2週間程度の潜伏期間の後、38度以上の発熱や、消化器症状(食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛)などの症状がでます。重症化し死亡することもあります。
ケムシ
チョウやガの幼虫のことで、毛に毒を持っていますが、全てのケムシが毒を持つわけではありません。身近なところではツバキやサザンカにつくチャドクガの幼虫による被害が多いようです。毒のある毛に触ると、赤い小さな発疹がたくさんでき、激しいかゆみを伴います。
ノミ
ネコやイヌに寄生する、体長2~3mmのネコノミ、イヌノミによる被害がほとんどです。ペットを室内飼いしている場合は、室内に成虫がいる場合もあります。刺されて1~2日後に赤い発疹と強いかゆみがあらわれ、水ぶくれができて初めて気づく人が多いようです。屋外ではすねや足を集中的に刺されます。
ハチ
庭木の手入れや農作業、ハイキングなどの際、アシナガバチやスズメバチに刺されることが多く、特に秋の野外活動での被害が多いようです。刺されてすぐに激しい痛みを感じ、数分後に腫れ始め、赤く大きくなり、強い痛みを感じます。
ミツバチ類は通常、刺激しない限り刺すことはありません。一般的には、ミツバチ類は1回だけ刺し、逆とげのある針を外して創傷内に残すことにより毒を注入し、刺した昆虫は死にます。メリチンがミツバチ毒の痛みを誘発する主成分と考えられています。ですから早めに針を抜く方がよいです。
スズメバチ類の針には逆とげがほとんどなく皮膚に残留しないため、複数回刺傷を負わせることができます。スズメバチの毒には、ホスホリパーゼ、ヒアルロニダーゼ、および最もアレルゲン性の高いantigen 5というタンパク質が含まれます。スズメバチ類も刺激しなければ刺されることはありませんが、ヒトの近くに巣を作るため、スズメバチを刺激する遭遇の頻度がより高いです。
ミツバチ類およびスズメバチ類に対する局所反応は、2~3cmまでの範囲の発赤、腫脹、および硬結を伴う、瞬時の灼熱感、一過性の疼痛、およびかゆみです。腫脹と発赤は通常48時間で最大となり、1週間持続することがあり、患肢全体に及ぶことがあります。初めて刺された場合、通常は1日以内に症状は治まります。しかし、2回目以降はハチ毒に対するアレルギー反応が加わるため、刺された直後からジンマシンを生じたり、刺されて1~2日で強い発赤や腫れを生じたりします。この反応には個人差が大きいですが、ひどい場合は刺されて30分~1時間で呼吸困難、腹痛、意識消失や血圧低下などを生じて、死に至ることがあります。これはアナフィラキシーショックと呼ばれる症状で、ハチ刺されによる死亡事故はこの特殊なアレルギー反応によるものです。
虫さされの治療
Treatment
軽症であれば市販のかゆみ止め外用薬でもよいですが、赤みや痒みが強い場合は副腎皮質ホルモン(ステロイド)の外用薬が必要です。虫刺されの多くは1~2週間以内に改善します。しかし症状が強い場合は抗ヒスタミン薬やステロイドの内服薬が必要になることがあります。ただ、これらの治療はあくまで現在の皮膚症状を抑えるのが目的であり、原因となる虫が身近に生息している場合は次々と新たな皮疹が出現する可能性があります。その場合は原因となっている虫を確認して、その駆除対策を実施する必要があります。
なお、刺された虫によっては、対処法や治療法が異なる場合があります。
ハチに刺された場合など、高度なアレルギー反応がある時は、全身性アレルギー反応に対するアドレナリンおよび抗ヒスタミン薬の注射、輸液、必要に応じて昇圧薬を用いて治療します。ミツバチの針があれば除去するなどの処置が必要になります。
痛み、熱感、およびかゆみが強ければ、できるだけ早く冷やし、経口のH1受容体拮抗薬、非ステロイド系抗炎症薬(NSAID)、またはその両方を投与することで軽減できます。
中等度のアレルギー反応は抗ヒスタミン薬の静注で治療します。